【数学アレルギー克服】中学数学は「暗記」じゃない!「パズル」だと思えば急に楽しくなる理由
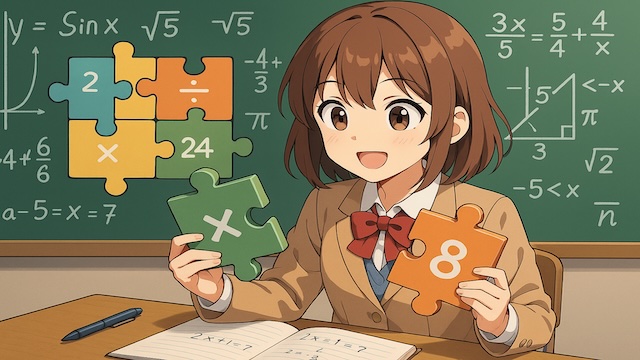
突然ですが、あなたは(あるいはあなたのお子さんは)、数学が好きですか?
「見るのも嫌」
「公式を覚えるのが苦痛」
「そもそも、何の役に立つのか分からない」
もしそう思っているなら、少しだけ私の話を聞いてください。
私もかつては、数学の教科書を開くだけで眠くなる「数学アレルギー患者」でした。
でも、ある日気づいたんです。
「あれ? これ、勉強じゃなくて『パズルゲーム』なんじゃないか?」と。
その瞬間から、苦痛だった数学の時間が、「解けないと悔しい!」「解けると超スッキリ!」というエンターテイメントに変わりました。
今日は、私が数学を得意科目に変えた最大の秘訣、「数学=パズル説」についてお話しします。
多くの人が陥る「暗記の罠」
数学が苦手な子の99%は、数学を「社会や英単語のような暗記科目」だと思っています。
- 「この公式を覚えなきゃ」
- 「この解き方を丸暗記しなきゃ」
これでは、つまらないのは当たり前です。
例えるなら、RPG(ロールプレイングゲーム)の攻略本をひたすら書き写しているようなものだからです。
ゲームの楽しさは、攻略本を覚えることではなく、実際に敵を倒してクリアすることですよね?
中学数学は「道具を使った謎解きゲーム」だ
中学数学、特に「方程式」や「図形」は、完全にパズルです。
ルールは簡単。
「手持ちの道具(公式や定理)を使って、隠された宝物(答え)を見つけ出す」。
ただこれだけです。
例えば「方程式」は「天秤パズル」
例えば、こんな式があります。
\(2x + 6 = 14\)
これを「移項して…符号を変えて…」と作業的にやるから面白くないんです。
これは、「天秤(てんびん)」のゲームだとイメージしてみてください。
- 真ん中の「=」は、天秤が釣り合っている状態。
- 左のお皿に「\(2x\)」と「重り6個」、右のお皿に「重り14個」が乗っています。
- 目的は、正体不明の箱「\(x\)」の重さを暴くこと。
どうしますか?
邪魔な「重り6個」を左のお皿から捨てたいですよね?
でも、勝手に捨てたら天秤が傾いてしまいます。
「じゃあ、右のお皿からも同じく6個捨てれば、釣り合ったままだ!」
これが方程式の正体です。
計算ではなく、「どうすればバランスを崩さずに箱(\(x\))だけを残せるか?」というパズルを解いているだけなのです。
\(2x = 8\)
\(x = 4\)
「解けた!」の快感はドーパミン
パズルや知恵の輪が解けた時、「あー!そうだったのか!スッキリした!」という感覚になりますよね?
あの瞬間、脳内にはドーパミン(快楽物質)が出ています。
数学も全く同じです。
- 補助線を一本引くだけで、見えなかった三角形が見える(=名探偵のひらめき!)
- 複雑な式が、どんどん約分されて最後に「1」になる(=テトリスが消える快感!)
平均点以下の子たちは、この「パズルが解けた時の快感(ドーパミン)」をまだ味わっていないだけなんです。
一度この快感を知ってしまうと、数学は「やらされる勉強」から「自分から解きたくなる遊び」に変わります。
私の指導は「パズルの解き方」を教えること
私が新しく始めたオンライン家庭教師サービスでは、難しい講義はしません。
「パズルのルール」と「道具の使い方」を教えます。
- 「この問題は、どのアイテム(公式)を使えば攻略できるかな?」
- 「ここは難しそうに見えるけど、視点を変えると抜け道があるよ」
そんな風に、隣で一緒に謎解きを楽しむパートナーでありたいと思っています。
もし、お子様が数学を「苦痛な単純作業」だと思っているなら、ぜひ私に会わせてください。
数学を「楽しいパズル」に変える魔法を、一緒にかけていきましょう。
お知らせ:無料カウンセリング受付中
「うちの子もパズル感覚ならできるかも?」と思われた方へ。
まずは現在の学習状況を聞かせてください。
「どこでパズルのルールが分からなくなっているか」を診断する、無料カウンセリングを実施中です。
👇 詳細・お申し込みはこちらから
「勉強」という言葉を使わずに「攻略」「アイテム」という言葉を使うだけで、子どもたちの目の色は変わります。
一緒に中学数学を攻略しましょう!







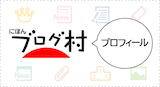
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません